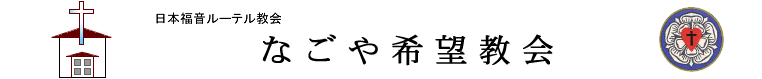| ルーテル教会は、マルチン・ルターの宗教改革により生まれたキリスト教プロテスタント教会です。人は信仰のみにより神より義とされ、恵みのみ、信仰のみ、みことばのみという改革の精神を大切にします。 |
Copyright(C)Kibou Church,Aichi Japan All Rights Reserved. |
| 2013年12月22日 末竹十大牧師 「大いなる低さ」 ルカによる福音書1章46節~55節 「何故なら、主が好意をもって眺めたから、彼の女奴隷の低くされていることの上に。」とマリアは歌う。マリアにとって「低くされていること」とは、彼女の身分の低さではなく、彼女の境遇であった。主なる神の意志によって、聖霊による身籠もりを与えられたマリアは、一端は受け入れた。しかし、受け入れた困難の先行きを思うとき、思い惑うものである。マリアも人の子。自らの決断ではない神の意志に身を委ねてもなお、不安が起こる。それゆえに、マリアは天使ガブリエルが教えたエリサベトの懐胎を確認に行く。エリサベトが如何にして、この不可思議な懐胎を受け入れたのかを確認に行く。そして、エリサベトから祝福の言を聞くのである、「わたしの主の母」と。エリサベトから祝福されたマリアが歌う歌が「マリアの讃歌」である。その始まりは「大きくしている、わたしの魂は、主を」と歌われる。マリアの「魂」、マリアのいのちが主を大きくするということは、彼女のすべてとなっている主であるという意味である。エリサベトの言を聞いたとき、マリアは自らが不安に思っていた困難を、主の大いなる恵みとして受け取ったのだ。エリサベトもそうであったと。 エリサベトが幸いであるのは、マリアを祝福することができるからである。人を祝福することができること。それこそが、その人の幸いである。もちろん、エリサベトとマリアの境遇は違う。エリサベトは不妊の女だったために、低くされていた。無価値な女とされていたのだ。そのエリサベトの苦しみ、悲しみに応えてくださった神は、マリアの胎に子を宿らせる神でもある。マリアに困難を押しつける神でもある。エリサベトは無価値な者から認められる存在に変えられたからこそ幸いだと思える。しかし、マリアは結婚もしていない状態で、子を宿すのである。彼女は子を求めてもいない。一方的に神から押しつけられ、困難な状況に陥れられたのだ。エリサベトとは違うと思える。ところが、マリアはエリサベトに出会ってから、マリアの讃歌を歌うのである。 マリアは歌う。「低められていること」に好意を持って眺める神を。「低められていること」とは彼女の苦しい境遇である。そこに目を留める、好意をもって眺める神を歌うのだ。どうしてなのだろうか。彼女のうちに何が起こったのだろうか。彼女の境遇が変わったわけではない。エリサベトは境遇が変わったがゆえに幸いだと思える。しかし、マリアの境遇は悪い方向へ向かっている。困難な状況は、変わりなくあり続けている。それなのに、マリアはそこに目を留め給う神を讃美するのである。 我々は目を留めてもらえることを喜ぶ。認められることを喜ぶ。わたしは目を留めてもらえるほど価値があるのだと思う。人の目を気にするのも同じ価値観である。目を留められないならば、わたしは価値無き者と思えるからである。マリアは人間からは価値無き者以上に、不貞の女というレッテルを貼られてしまうような境遇である。人間からは絶対に認められない自分自身を知っている。その状況は何も変わらないのである。神が目を留めた、好意をもって眺めたとしても、彼女の状況は変わらないのである。変わり得ない状況を知りつつも、彼女はどうして神を讃美するのだろうか。 普通ならば、彼女の状況が好転してこそ、「神さまありがとう」と言うであろう。好転しなければ「神さまはわたしを見捨てた」と思うであろう。「エリサベトは幸せだけれど、それに比べてわたしは」と思ってしまうものである。それが通常の反応である。ところが、マリアは違うのだ。状況の変化は起こり得ない。状況がさらに続いていく、子が生まれるまで。好転しないで、低められているだけのマリア。このマリアは何を見たのか。何を聞いたのか。「低められていること」の幸いを見たのだ。祝福を聞いたのだ。エリサベトの口を通して、神の祝福を聞いたのだ。「低められていること」は幸いなのだと聞いたのだ。 どうして「低められていること」が幸いなのか。高められることが幸いではないか。確かに、マリアは「低められている者を高める神」を歌っている。しかし、マリアの状況は変わり得ないし、この世で低められている者の状況も変わり得ない。たとえ、信仰が与えられてもなお、現実の状況に変化はない。ただ淡々と続いていく現実があるだけなのだ。ところが、この現実こそが実は幸いであり、神の祝福であるとマリアは歌っているのである。変わり得ざる現実をわたしは生きることができると歌っているのである。それはマリア自身が変えられたからである。 49節でマリアは歌っている。「何故なら、わたしに行ったから、大きなことを、可能な力を持つ方が」と。「大きなこと」とは処女懐胎であると思いがちである。しかし、マリアが歌う「大きなこと」とは不可能なことを可能にする力によるのである。そうであれば、マリアが担いきれないと思う「低められていること」を担うことが可能とされるという意味である。単に処女懐胎という不可思議なことをする神を歌っているのではない。マリアは、神の可能とする力によって、彼女の境遇を「大いなる低さ」として生きて行くことができると歌っているのである。それこそが、イエス・キリストの母マリアに与えられた信仰なのだ。 この信仰は、使徒パウロが第二コリント12章9節でキリストから聞いた言として述べているものである。「わたしの恵みはあなたに十分。何故なら、神の可能とする力は、弱さの中で完成する。」と。パウロが言う「弱さ」とマリアが言う「低められていること」とは同じである。「弱さ」は「低められていること」である。その「低められていること」と「弱さ」との中でこそ、人は真実に生きることを見つめることができるのだ。わたしの「低められていること」を神が好意を持って眺める視線を受けることができるのである。高慢な者は、神の視線を受けることができない。何故なら、彼らは神など必要ないからである。自分の力に頼っていれば良いのだから。しかし、その力もいずれ失われる。権力の座についていても、すぐに追いやられてしまうのである。反対に、「低められている者たち」は追いやられることはない。むしろ、そこにおいて雄々しく生きて行くことができるのだ。何故なら、彼らは自らの力に頼れないことを知っているからである。ただ、自らにないものを渇望しているからである。「良い物」と新共同訳が訳しているのは、「本質的に善きもの」、ギリシャ語でアガトスのことであり、聖書では「神ご自身」を指す。イエスが金持ちの青年に答えたように。「誰もいない、善きものは、一なる神以外には」と。従って、善きものを渇望している「飢えた人」は、神を渇望しているのである。神を渇望するほどに「低められていること」こそ幸いである。その人には、神がすべてだからである。神がすべてになるほどに「低められていること」こそ「大いなる低さ」なのである。誰も獲得することのできない「大いなる低さ」。この「低さ」の中で、神の可能とする力は完成するのだ。人間の力はそこでは否定されている。神の力がすべてである。マリアの讃歌は、神の力に包まれたマリアに与えられた神の言である。マリアの胎に宿っている神の言なのだ。 マリアの胎の子は、究極的低さである十字架に至る。究極的「大いなる低さ」はキリストの十字架である。パウロはキリストについてこう言っている。「何故なら、キリストは弱さから十字架に架けられたからです。しかし、神の可能とする力から生きている。」と。キリストは弱さを起源として十字架に架けられた。しかしその中で、神の可能とする力を起源として生きている。従って、弱さの中でこそ神の可能とする力は完成しているのである。マリアは、このイエス・キリストの母である。彼女が受け取った神の可能とする力は、彼女だけではなく、神を畏れ、神の善きものを渇望する人々のうちに働くのである。我々に与えられた神からの信仰は、「大いなる低さ」の信仰である。キリストの体と血に与る我々は、この信仰を受け継ぐのだ。神の国に至るまで、この信仰によって歩み続ける。如何なる困難をも神の恵みとして引き受け生きるのである。 |
|